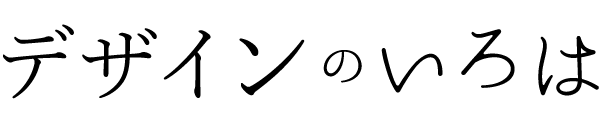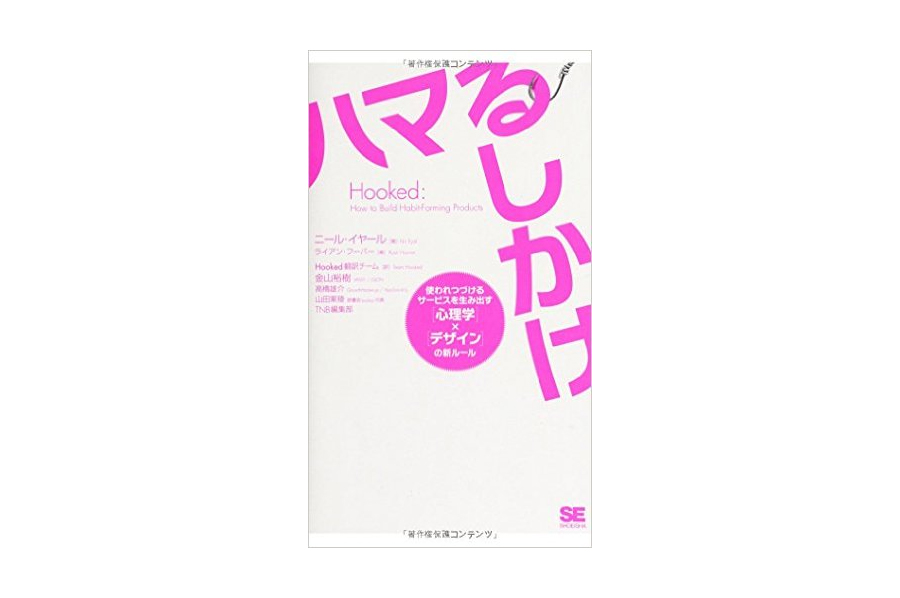画像引用:amazon
デザインには認知科学要素も多く必要になるので、そういった意味で手にした本。
本のボリューム的にはそこまで多くなく、サクッと読めて内容も読みやすい本でした。
本の概要
facebook、twitter、Pinterestなど、実際にあるサービスを元になぜユーザーがサービスを利用し続けるのか、なんとなく思っていることをしっかりと体系化してまとめている本です。
ユーザーに絶え間なくサービスを利用し続けてもらうには「習慣」を形成できるかどうか。
その「習慣」はきっかけ(トリガー)、投資(インベストメント)、報酬(リワード)、行動(アクション)のフック・モデルでできている。
プロダクトやサービスの習慣を形成するポテンシャルがあるかどうかは「頻度(その行為がどれくらいの頻度で発生するか)」と「使いやすさ(ユーザーにとってその行為をすることが、既存のソリューションと比べてどれほど便利で利点があるか)」
読書からの考察
人が行動を起こす3つの要因
- 十分なモチベーションを持っている
- 行動するための能力を持っている
- 行動を起こすトリガーが存在する
モチベーション
モチベーションは行動する為のモチベーション。これがないとそもそも行動を起こさない。つまりここが行動を起こすトリガーになる。広告がユーザーのモチベーションに影響を与える。見た目によるモチベーションの制御も可能。
しかし、対象のユーザーをしっかりと熟知しなければ、まったく馴染めないものになってしまう場合がある。
恐怖心を煽って行動につなげさせるパターンもある。運転免許証更新の際に見せる交通事故の悲惨な映像を見せるのはその一つかと。
行動、トリガー
行動が起きる可能性を増やすためにはシンプルさに重点を置くこと。ユーザーにとって何が邪魔になっているか、その何かを見つけること。ビジュアルデザインで例えると必要なものを目立たせる。余計な要素を追加しない。twitterのwebページの進化は面白い。どんな人に行動(登録)を起こしてもらいたいかビジネスの成長や今、自社がどんな位置にいるのか、しっかりと確認してそれをデザインに反映してユーザー数を獲得していくプロセスは流石といったところです。
利益を優先することで、サービスを純粋に楽しめないものにしている
「不幸なことに、あまりにも多くの企業が、ユーザーがしたいと思うことをさせるのではなく、ユーザーにさせたいと思うことに基づいて、プロダクトを作っている。企業がユーザーの行動を変化させることに失敗するのは、利益を優先することで、サービスを純粋に楽しめないものにし、これまでの行動をシンプルにさせることなく、新しくて不慣れな行動をユーザーに覚えさせようとするためである。」これは製作者も無意識にやってしまうことが多い。こうならない為に何度もユーザーは何がしたいのかという本来の欲求に立ち返る必要がある。
行動を変化させるには、ユーザー自身が主導権を握っているという感覚を保証しなければならない。ユーザーはサービスを義務的に使いたいのではなく、自主的に使いたい。
イケア効果
これまた面白い効果。
イケアのユーザーは自分で家具を組み立てることでその家具に愛着を持つ。人間は何かに投資した結果それを正当化する。イケアのビジネスはユーザーが製品に労力を費やしたという理由で、製品により高い価値を与えられる。ユーザーは自らの作業を通じてその製品に投資をしたといえる。
所感
認知科学系の本は「あーあるある!」といったものがあって面白い。
今回のこの書籍の場合、ユーザーに繰り返しリピートして利用してもらうにはといった心理的なアプローチは参考になる一冊でした。
全てのプロダクトやサービスにはリピーターのみがとる一連の行動パターンが存在する。どのステップがリピート行動へのきっかけとなっているかを明らかにして、そこを強化する。これこそ本書が一番言いたかった事ではないかと思います。