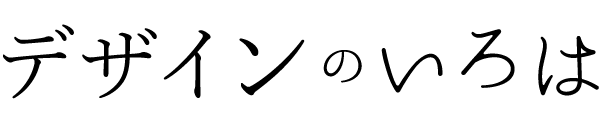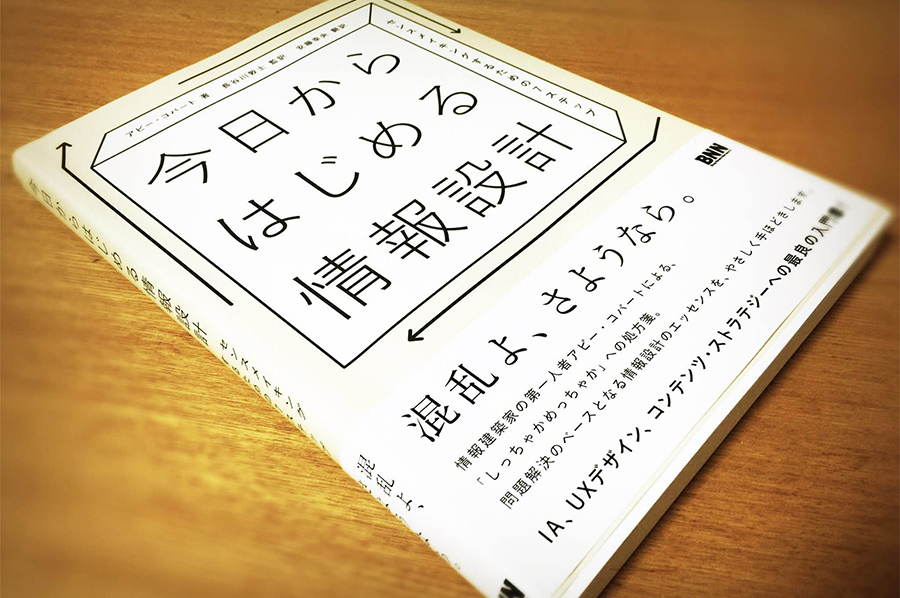本の概要
本のタイトル通りこれから情報設計を初めて行う人や、これまで情報設計を行った人でも新たな考え方が学べる本ではないかと思います。
情報設計の手法や情報とは何か情報を整理するにはどうしたら良いのかwebの仕事以外にも広く使える考え方が得られる内容になっています。
読書からの考察
情報は主観的であり客観的ではない
例えば「10人中8人の医者がお勧めしません」というのと「医者がお勧めしています」というのは同じであるが情報の受け手によっては捉え方が変わる。
情報の受け手であるユーザーとステークホルダーについて深く考える
ユーザーは誰なのか?
ユーザーについて何をしっている?
どうすればユーザーをもっと知ることができるだろうか?
ステークホルダーは誰なのか?
ステークホルダーが期待していることは何なのか?
ユーザーのチャネルとコンテクストをまとめる
例えばテレビ番組を見ながらその番組についてツイートするとしたら、ユーザーのコンテクストは
「ソファーに座りながら、自分が観ているものについて、自分の反応を共有しようと思うほど興奮している」ということになる。
このコンテクストでユーザーは異なったチャネルを使っていて、この場合のチャネルはtwitter、スマートフォン、テレビを利用している。
何を良しとするのか。良いとは何か?
「良い」や「悪い」といった単語の定義の仕方を決める
ステークホルダーとユーザーに対して、何が「良い」のかを定義していないとき、言葉を有利につかえない。
何が良いことかを明確に理解していないと、意思決定の際、ほとんどが一部のステークホルダーの意見に従わないといけなくなる。
それが悪い意見であっても。
そして「良い」情報設計を実践するためには、良さの意味を定義しなくてはならない。
そしてこのような類いの集中が必要なのは、設計段階だけではなく、もっと以前の段階である。
所感
普段生活していると、色んな所から流れてくる情報。
みんなが同じように情報を解釈していると思いがちだが、実はこれが主観で受け手により解釈が異なることに改めて気付かされる本でした。
ただ、”情報設計”といっても一般的な方からすると馴染みのないもので情報設計とはそもそも何なのか。それをする事でどんな効果が得られるのかといった事の説明は必要であると思いました。
本書でも触れられているのですが「良い情報設計ですね!」と一般的にユーザーから言われる事はまずない。
ただ情報設計の悪いものに関しては印象に残る。
良くできたものこそ、その存在を感じさせなく自然に人に寄り添うものなのではと思います。