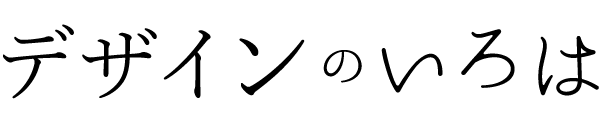amazonのネイティブアプリではないスマートフォンサイトのUI(ユーザーインターフェース)について考察。
長くなるのでトップページのヘッダー付近のみ考察。
目的の商品を素早く見つけ出し、そして購入までの意思決定までも支援する
まず視界にすぐ入るのはトップのヘッダー部分、大きく視界に入るのは「検索フォーム」
amazonのブランドカラーであるイエローを検索ボタンに採用することで検索フォームの大きさだけでも十分目立つのですが更に視界に入りやすいデザインになっているのが伺えます。
そして検索フォームの下にはポイントが表示され、購入のする際の背中を後押しする様な流れです。
amazonを利用するユーザーの文脈(コンテクスト)を考えるとamazonのサイトを訪れている時点で既に購入するものが決まっている事が多いと思われます。
つまり、具体的な商品名も既に決まっていて、その商品名をすぐに入力しやすい状態ができていて、且つ、ポイントを表示する事で購入する際の意思決定までのスピードを早めているのではと考えられます。
これはサインインしていても、していなくても、ほとんど同じデザインになっています。
ヘッダー部分でログイン前と後で異なるのはポイント表示がされているかされていないかのみです。
検索フォームがフッター付近にあるとどうだろうか?
毎度フッターまで何度かスクロールしてようやく検索。
かなり使いづらいものになると思われます。当たり前の様に思えるのですが、実際こういったユーザーの文脈(コンテクスト)を考えずに「ただ配置した」ということが多いです。
文脈(コンテクスト)だけでなく、そもそもユーザーは誰なのかといった定義が決まっていないことがほとんどです。
サインインの後サインアウトの文字にならない理由
ヘッダー部分のサインイン部分の表示はサインイン後、会員の名前が表示されます。
これはどのデバイスで見ても必ず上部の方に配置されているのですが、amazonのお家芸でもあるパーソナライズドされたレコメンドが表示された際、どのユーザーに対してのレコメンドを表示しているかを混乱させず明確に伝えるためではないかと思います。
例えばタブレットなどでは家族全員がタブレットを使用してamazonを使用するシーンが想定されるので、家族の誰へのレコメンドなのか混乱を解消するものと考えています。
ハンバーガーメニューがない理由

実はamazonのネイティブアプリの方はハンバーガーメニューが実装されていて、スマートフォンサイトの方はハンバーガーメニューがないデザインになっています。
考えられる要因としてアプリをインストールするユーザーは既にサービスをよく利用するユーザーとしていて、注文履歴やほしい物リストアカウントサービスなどアクセスしやすくする為にハンバーガーメニューを実装していて、スマートフォンサイトで購入する場合は一度買いなど頻繁にサービスを利用しない人にとっては注文履歴やほしい物リストなどの情報は邪魔でしかないため大胆にもハンバーガーメニューをなくしているのではないかと思います。
機能は多ければ良いというものではない
ハンバーガーメニューと同様に、何でもあれば良いという事はありません。
情報が多くなればなるほど見た目は複雑になります。
つまり簡単に使えそうと思っていたものが、瞬時に複雑に見え使い勝手が悪くなることも少なくありません。
よく私は日本のテレビのリモコンの例を例えるのですが、日本のリモコンには、ほとんど使わないボタンなどたくさんあります。
ほとんど使わないものや情報はユーザーにとってノイズになります。
あれも、これもと情報や機能を追加する前にユーザーにとって本当に必要なサービスになっているか考えてみませんか。