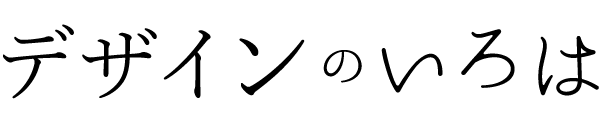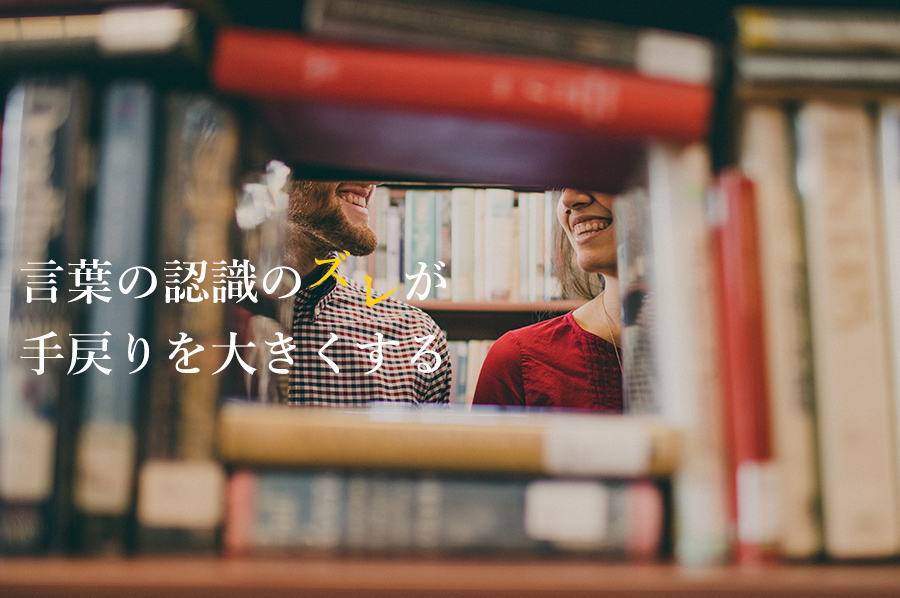伝言ゲームのズレは、なぜ大きくなるのか
一度は誰もがやった事があると思う伝言ゲーム。
最初に話した人の内容と最後に話しを聞いた人の内容が全く違う内容になっていたりすることがあります。
このズレがデザインやプロジェクトの手戻りを大きくする要因の一つと考えています。
間に入る人の多さも一つのズレの確率を上げる要因になると思いますが一番は言葉に対する認識の違いや先入観で起こるものだと思います。
単語の解釈は人それぞれ
- ○○が難しい。
- ○○するのが面倒臭い
- ○○の様なかっこいいデザイン
- ○○の様な優しいイメージ
- 簡単に○○できる
それぞれ「難しい」「面倒臭い」「かっこいい」「優しい」「簡単に」と単語がありますが、例えば「難しい」とは、どういうことを難しいといっているのか?
「面倒臭い」とはどういう事が面倒臭いといっているのか、普段会話しているなかでは、ほとんど自分の中で思い込んで聞き返す事はしないと思います。
「恐らく、こういう事を言っているんだろう」と解釈した時点で既に会話している人どおしのズレが生じている可能性があります。
仮説を持たずに言葉の定義をズレのないように聞き返す
「難しい?」とオウム返しで聞いてみるのも良いし、「○○が難しいとはどんな事ですか?」と聞いてみたりする事で言葉のズレが少なくなります。
仮説をもって会話すると思わぬところで誘導尋問になったり、聞き返す事の注意が薄れたりするので、まずはありのままの言葉を受け入れて聞く事に専念することがズレをなくすポイントになると考えます。
聞くときだけでなく、話すときもズレを意識する
プロジェクトメンバーに伝える際も、単語に気をつけてなるべくズレがない様に意識的に話すことがズレを小さくすることにつながると思います。