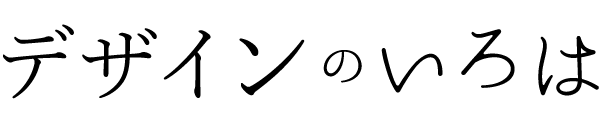「神話の源流へ。」ポスターをUX(ユーザーエクスペリエンス)の視点で考察してみました。
目的は何なのか?
私がこのポスターを見たのは宮崎駅。
少なくても宮崎駅にポスターが掲示されているという事は、宮崎駅でのポスターの目的は観光の目的が大きく占める事が予測できます。
※ポスターだけでなく冊子などにも展開されていますのでポスターという観点で考察していきたいと思います。
UX(ユーザーエクスペリエンス)とは
UX白書で構成されているUX(ユーザーエクスペリエンス)は簡単に説明すると下記の要素で構成されます。

引用:http://site.hcdvalue.org/docs
このポスターの場合、体験を想像する段階(サービス利用前の予期的UX)が最も大きな役割を担うと考えられます。
ポスターを見た人(ターゲット層)が「美しい景色!行ってみたい!」とモチベーションを上げる事が大きな役割となります。
次にモチベーションがあがったユーザーがとりうる行動として、スマートフォンでの場所の検索。
若しくは人にポスターに掲載されていた場所を聞く。
といった事が考えられると思います。
次の行動を起こすまでに何が邪魔になっているかを見つける
宮崎駅ではこのポスターが駅のホームへ上がるエスカレーター(上りのみ)の所に貼られています。

ユーザーがこのポスターを見るのは切符を買ってホームへ上がる時に見る機会が多いと思われます。
この後、スマートフォンで検索する場合、ポスターの左下に小さく書かれてある場所を覚えているのかといった一つの懸念が浮かびます。
また、駅のホームへ上がる時の場所に掲載されているとユーザーは既に行き先が決まった状態(切符を購入した後)の時に目にする事が多くなります。
つまり、ポスターを見せるタイミングがもう少し早い段階でターゲット層のユーザーに見せれると行動に移す結果が変わる可能性があります。
適切なタイミングで適切なデザインを
宮崎駅には駅の中央に待合のベンチが幾つか並べられています。宮崎の電車の運行は、ほとんどが1時間に1本程度で、電車を逃すと、このベンチで待つ機会が多くなります。
電車が来るまでスマートフォンを触ったり、本を読んだり、友人と一緒であれば友人と話したりして時間が来るのを待ちます。
何かを見て、それについて調べるには絶好の場所になると思います。
つまり、この場所に今回のポスターがあるとポスターの場所など、より探しやすい環境ができていると考えます。
松波晴人さんの行動観察の著書にもポスターの貼る位置で売り上げが上がる実績が描かれています。
著書ではスーパー銭湯で女性が浴衣姿でビールのジョッキを持っている、いわゆるよく見かけるポスターをサウナの中に貼ることでビールの売り上げが59%アップした例が記載されています。
同じ提案内容であっても提案するときのコンテキスト(文脈)が非常に大事です。
宮崎駅の中で掲載物の色々な事情もあると思いますが。
デザインには一気通貫のデザインのマネジメントが必要
エムテド代表の田子学さんも仰る様にデザインは一気通貫のデザインのマネジメントが必要です。
デザインのほとんどが制作することだけという見方が多いのですが、今回のポスターひとつでもポスターの見た目を作るだけではデザインの効果は最大限に活かしきれません。
ポスターを見る場所、ポスターを見た後のユーザーの行動に沿ったサービスデザインが必要になります。
デザインはポスターやwebの見た目の製作だけでなくユーザーの行動から全体のデザインを考えるUX(ユーザーエクスペリエンス)デザインを考慮した上で見た目や情報のあり方を考える必要があります。
こういった考えがないと所々でデザインの効果が途切れ途切れになるのは否めないでしょう。