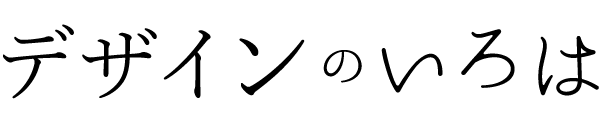良いデザインはマニュアルがいらない
村田智明さん著書の行為のデザインでは
「説明書は一見親切ですが、本質を見れば不親切です。なぜならユーザーは操作のためにまず言葉というメディアを体験しなければならず、ユーザーが本来求めている行為以外で時間を費やさなければいけない」と書かれています。
確かに良いデザインはマニュアルがいらないし、そもそも間違った操作をさせずらくしているものが多いと思います。
マニュアルを読まずにモノゴトができるのは理想ですが、何もかもがマニュアルがいらないかというと、そうでもないかなと思います。
できるだけマニュアルを見らずに済むにはといった形でUIがデザインについて考察しました。
発券機UIの課題は何か?

写真を見ると「ここをタッチ」「ご希望のボタンをタッチ」「お金を入れる前にタッチしてね」と事前に画面のシュミレーションを見せる事でユーザーの操作の誤りを少なくしてスタッフへの問い合わせ数の減少やユーザーが操作を間違う事でストレスを感じる事を現象させるという推測ができる。実際にそうかどうかはわからないですが。
仮説を立てるとすると、恐らく一画面に選択するボタンつまり選択肢が多すぎて何を選択したら良いかわからないののではないかと。
どうしたら解決できるか?

ユーザーの心理的側面や思考を考慮すると田舎の駅では発券機に列ができることはまずないですが、列ができることを想定するとユーザーは「早く買わなきゃ。待ってる人がこんなにいる。」と焦る状況もあり得るのかなと。発券機の操作に慣れていない人ならなおさら心理的に焦る状況になるのではないかと思います。
そんな心理状況の中で選択肢が幾つも用意されていると、普段の心理状態であれば迷わないものでも、どれを選択すればよいのか余計に迷ってしまう事もあると思います。
情報を見せる順番も大事
電車に乗る時点で何よりも頭の中にあるのは目的地の事ではないでしょうか。
目的地と頭の中にあるのにいきなり乗車人数や片道なのか往復なのかといった情報が先立ってでてきて最後の最後で目的地の選択がでるとどうでしょうか?
心理的に不安になったり、表示される情報の順番が異なるだけで頭の中で考える時間が増えストレスを感じる事が増えます。
見せるべき情報の順番と表示する情報を分ける
例えば、まずは目的地を選んでもらう情報だけを見せ、次に何人でいくのか、その後往復なのか片道なのかといった形で順序立てて選択していくUIになっていると前述した心理側面などを考慮しても選択しやすくなるのかと思います。
こうすることで一度に選択する時よりも画面数が増え遷移する回数も増えてしまいますが一度に選択する数が少なくなるので選択しやすくなります。
細かく見ると人数のアイコンも更に良くできる

大人一人、子ども一人はまだわかりやすいのですが、大人二人で子ども一人の場合や、子ども二人で大人一人の場合、大人二人で子どもふたりの場合のアイコンが瞬時に判断するには少しわかりづらく感じます。
子どもを大人二人が挟む、大人を子ども二人が挟むなど仲の良い家族感の様な印象は受けるのですが、左に大人、右に子どもが並ぶといったルールがあると瞬時にわかりやすくて選択する時間も短縮できるのかと思います。
モノからデザインするのでなくコトを考えてモノをデザインする
UI(ユーザーインターフェース)デザインと言葉だけで見ると、よく一般的に連想されるのは画面のデザインですが、この考えだとモノ(画面)中心のデザインに視点がいきがちで、ボタンの押しやすさ、装飾など視覚的部分に議論が移ってしまいがちです。UIは画面デザインだけでなくサービスとユーザーが接する所という考えのもとにデザインがされていないと使い勝手の良いものはできません。
つまりモノでなく「コト」を考え「モノ」を作るということが必要になります。
これはUIデザインだけでなく他のデザインでも同じです。