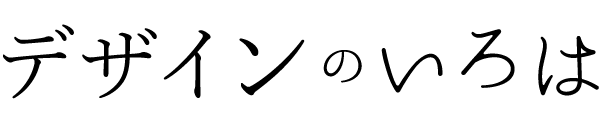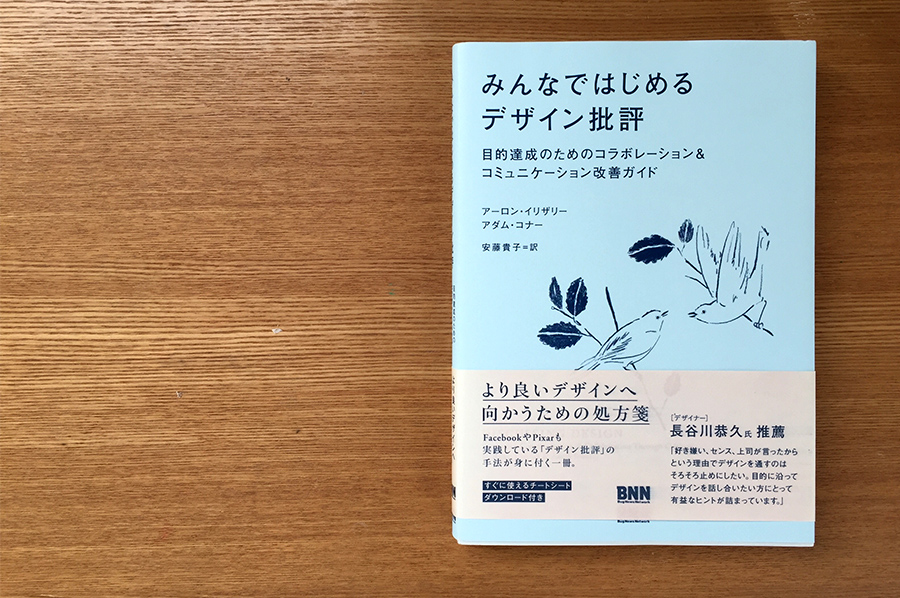制作したデザインへのレビューのやり方が記載してある本で、しっかりと体系的にまとめられた本です。
例えば、レビュー前の準備やレビューする側、受ける側の心構えや、やり方など具体的に記載されています。
デザイナーでなくてもデザインのレビューはできます。この本はデザイナー、ノンデザイナー両社へのレビューの手引書になると思います。
主観でなく目的・ゴールに沿ったデザインレビュー
デザインレビューを行うとほとんどが声の大きい人(決裁権を持った人)の主観によるデザインの変更を余儀なくされる事が多いです。
主観によるデザインのレビューほど、役に立たないものはないです。
本書では
- デザインをする目的は何なのか
- その目的のゴールは何か
- その目的に関わるユーザーはどんな人か
- そのユーザーはどんな時にデザインしたものを利用するのか
など順序立てて、声の大きい人の主観ではなくステークホルダーのコンセンサスの指標を作り、目的やゴールに沿ったデザインのレビューの方法が記載してあります。
そもそもこれを実施するのにはデザインレビューの段階では遅いのですが、しっかりと目的や戦略に沿ったデザインを行うにはどうすればよいか参考になると思います。
答えではなく道筋を述べるデザインレビュー
デザインで意見をもらう場合、もう少し色は濃くやフォントは◯◯でといった答え(指示)をする事が多く見られるのですが、この後に道筋(理由)を付け加えることでデザインの議論ができ多くのアイデアが生まれる機会になることが書かれています。
この理由がないということは、主観で言っているのと同じで、「なぜなら~」といった形でレビューをする事を推奨しています。
尋問の様な質問の仕方をしない
レビューする側は相手をイライラさせたり責めるような気持ちにさせない。レビューする側、される側に上下関係はなく皆平等。
「なぜ?」「どうして?」といっては強制的に返答させている様な聞き方になります。
「・・・・について詳しく教えてもらえますか?」といった気楽に答えられる様な質問をする。
このルールを見てユーザーインタビューと同じだと思いました。本音を聞きたい時に「なぜ?」などの質問をすると強制的に相手は答えを返さないといけない状態になります。
これでは本音も聞けません。
総評
デザインレビューの本というだけで恐らくそんなに数はないと思いますが、そんな中でもしっかりと目的に向かってデザインするにはどうしたら良いのか、どういう風にレビューしたら良いのかまとまっている本でした。
デザイナーだけでなくデザインで手を動かさない方こそむしろ読むとプロジェクト成功へ近づくのではないかと思います。