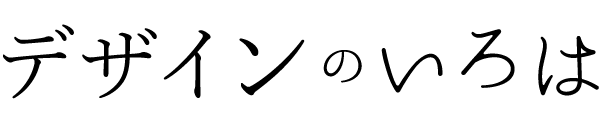一般的に言われているユーザビリティという概念は「使いやすさ」というのは認識されているのですが、よくあるのが個人の主観で「これ使いづらい」などという評価される事が多くあります。
ユーザビリティは主観ではない
ISO 9241-11では、「特定の利用状況において、特定のユーザによって、ある製品が、指定された目標を達成するために用いられる際の、有効さ、効率、ユーザの満足度の度合い」と定義されています。
ここでもまた、5w1hがでてくるのですが、「いつ」、「どこで」、「誰が」、「何を」、「なぜ」、「どのように」利用されるのか、利用状況が定まっていないとユーザビリティは評価できません。
なぜなら利用シーン(上記の「いつ、どこでの部分」)一つとっても、どの情報を優先的に見せるのか、どんな形状が良いのか変わってきます。
例えば、webで駅の時刻表が知りたいという時に、最寄りの駅でなく東京駅の時刻表が表示されたらどうでしょうか?
自分の最寄り駅までを表示するのに何度も画面遷移しないと表示されないのでは使い勝手が悪いです。
この場合スマホであればGPSで現在地を取得して最寄りの駅を選択しなくても自動的に表示してくれると使い勝手がよくなります。
ユーザビリティを評価するには
ユーザビリティを評価するには上記で列挙した「いつ」、「どこで」、「誰が」、「何を」、「なぜ」、「どのように」利用されるのかをまず決めましょう。
よくあるのが、そんなに利用シーンや使う人を絞り込んで大丈夫なのかといった事が挙げられるのですが、万人に受けるものは結局、どこも尖らない平均的なサービスにしかならないです。
平均的なサービスであれば既にブランドが構築されている信頼のある大手ブランドのサービスを利用する人が多いでしょう。
UI(ユーザーインターフェース)デザインだけでなくコンテンツもユーザビリティ
webの場合、ユーザビリティというとUI(ユーザーインターフェース)などの操作性ばかり話題になるのですが、コンテンツそのものがユーザビリティになることが忘れられている事が多いです。
適切なタイミング(シーン)で適切な情報が提供できるコンテンツが用意されているか、これもユーザビリティの要素になります。
こう考えると「いつ」、「どこで」、「誰が」、「何を」、「なぜ」、「どのように」がないとコンテンツもできないと思います。
下記のコンテンツはミニバンの比較サイトですが、ユーザーがミニバンを選ぶ際に気になる情報を上手にまとめて比較ができるコンテンツです。
TOYOTA ミニバン徹底比較コンテンツ

以下の条件では、とても良いユーザビリティになるのではと思います。
- いつ→車を購入しようと思っているが、どの車を選んだら良いかわからない時
- どこで→自宅で
- 誰が→家族持ちの男性
- 何を→家族が乗るのにぴったりな車
- なぜ→現在所持している車の車検がもうすぐなので
- どのように→車の比較をする
通常だと多くのブランドの車のぺージへ遷移し比較しないといけない面倒さをこのコンテンツは解決しています。
なかでも下記の情報の分類の方法はユーザーが気にするところをとらえているのではないかと思います。

操作性だけでなく情報のあり方を考える
タップのしやすい大きさ、視認性の高さ、などユーザビリティでは操作性という概念が認識されていますが、根本的には情報構造のあり方がまず問われます。
操作性が良くても情報構造がしっかりとできていないと、いつまでたっても欲しい情報が見つからないというのはストレスの溜まる要因です。
操作性も勿論大事ですが、「いつ」、「どこで」、「誰が」、「何を」、「なぜ」を理解して適切な情報を提供するコンテンツを用意するのもユーザビリティに大きく関わります。