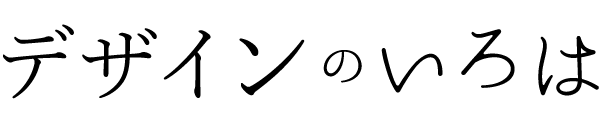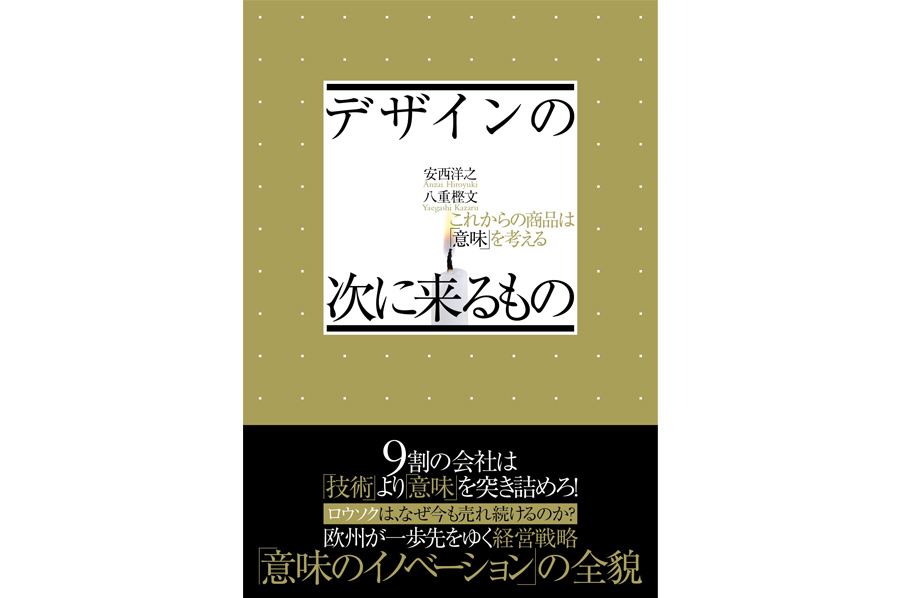タイトルからはどんな内容が書かれているか、わかりづらいですが「デザインとは何か?」日本でのデザインの捉え方、アメリカでのデザインの捉え方など各国のデザインの捉え方から「デザインの問いの立て方」が書かれている書籍です。
デザイン思考の捉え方
デザイナーだけでなく、経営者の方まで幅広く、「デザイン思考」という言葉をここ数年聞いたことがない方はいないのではないくらい広がっていると思います。
そのデザイン思考の問題点が書かれていて、私自身が感じていたデザイン思考の問題点と同じだったのが、安心したというか整理ができた書籍でした。
具体的にはデザイン思考は「問題の領域を設定し、その問題の本質を理解する」ことから始まり観察やプロトタイプを作成しテストするプロセスを繰り返すのですが、「問題の領域自体を自分たちで探求していけるかどうか」つまり「今何が本当の問題なのか?」問題解決でなく本質的な問題を見つける問題の捉え方が間違っていると、後のプロセス全てが無駄になってしまう事が指摘されています。
デザイン思考を理解する
本書ではただ、批判するのではなくデザイン思考を理解して、必要な場面を見極めて利用することも、しっかりと書かれています。
デザイン思考をやればイノベーションが起こせるという安易な考えで利用するのでなく、しっかりと場を見て必要に応じて使う。
そのためにはデザイン思考とは何なのか深く理解する必要があると思います。
また、デザイン思考はユーザーに寄りすぎて視野を狭くする危険性があるとこも指摘しています。
本書ではワインの栓抜きの実例が掲載されているのですが、ユーザーに寄り添ってユーザーはワインの栓をどんな風に開けるのかを観察しているのでは、ワインの栓を開ける道具の使いやすさだけに視点がいき、視野が狭くなります。
もちろんデザインを考える上で使いやすさを追求するのは大事なのですが、そこだけではなく次のように考えると栓抜きの使いやすさだけでなく、どこに視点を置くと良いのか視野が広がります。
「あなたの家族が、家で夕食をとる時、そこにどんなことを求めていますか?」
ワインの栓抜きという対象に最接近するのでなく、もっと引いて生活全体に視野が移ることで「問いの立て方」が変わります。
デザイン・ドリブン・イノベーション
前述のように問いの立て方を発見するのがデザイン・ドリブン・イノベーションと私自身は解釈しています。
探求されるものは「モノの物理的な質や機能ではなくモノに与える意味」つまり、なぜそれが必要なのかwhyを深く追求できる考え方なのではないかと思います。
著者のベルガンティは「人々は、実利的な理由だけでなく、深い感情的な理由や、心理的・社会文化的な理由からモノを買う。つまり人々は製品を買うのではなく、その意味を買っている」と記載しています。
そのモノの意味を劇的に変える方法論がデザイン・ドリブン・イノベーションと定義しています。
まとめ
UX(ユーザーエクスペリエンス)デザインのワークショップでも行なっている「上位下位関係分析」と共通しているところがデザイン・ドリブン・イノベーションにあると感じた一冊でした。
上位下位関係分析もまた、ユーザーは本当は何を必要としているのか下位の概念から上位へラダーアップしていき、「意味」を問う方法でこのあたりが個人的には通じるものがあると思った箇所でした。
タイトルからするとこれもまたデザインという、いわゆる見た目のデザインだと捉えがちですが内容は広義のデザインを指すものでデザイナーだけでなく、コンサルティングや経営者の方にとって良い書籍だと思います。
デザイナーは必読の本であると思います。