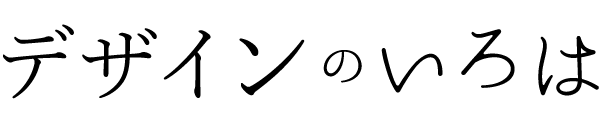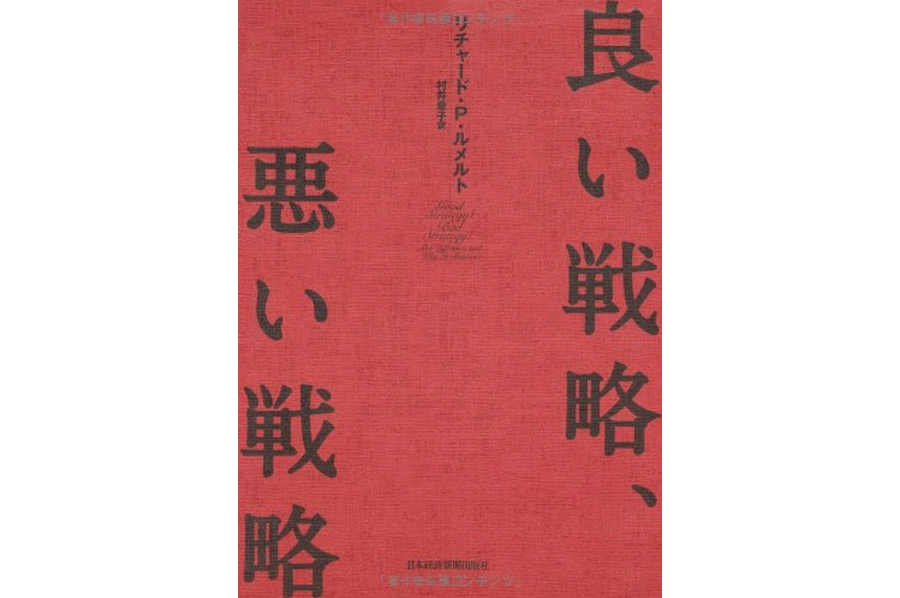画像引用:amazon良い戦略 悪い戦略
戦略と聞くと複雑で難しそうなイメージがありますが、どこまでシンプルに単純明快に落とし込めているか、これが戦略を立てる上でのスキルなのではと本書を読んで感じた点です。
本の最初の方では戦略とは何なのか?戦略自体を全く知らない方でも理解できる内容になっていて、後半は実際の名だたる海外企業や日本企業の具体的な戦略の考察が記載されています。
戦略を考える時に役に立つ本であることは間違いない書籍でした。
以下は本書で自分が特に印象に残った内容になります。
良い戦略というのは単純かつ明快
なぜ良い戦略というのは単純かつ明快なのか自分の考えとしては単純かつ明快であるほど実行しやすいから。
複雑であると実行する際も時間がかかり、戦略を理解するのも時間がかかる。だから良い戦略とは単純かつ明快だと思います。
人間は「考える」ということを避ける傾向にあります。なぜなら疲労を伴い無駄な時間を費やす事が多く特に自身が興味もないことを考える事に関しては顕著にでて考えることを避けます。
シンプルに考えることができシンプルに実行することができる。
何が課題なのか複雑に絡み合ったものをシンプルに落とし込みができる、ここに戦略を作るスキルがありシンプルに見えるもこその実は複雑なものであった経緯があることを意識しておかなければいけないと改めて認識させられました。
こちらの打つ手の効果が一気に高まるようなポイントを見極め、そこに狙いを絞り、手持ちのリソースと行動を集中する事
効果が一気に高まるポイントとは自社自身の強みを考慮した戦い方である。強みで考慮すべきは、その強みを必要としているマーケットがあるか。
マーケットがなければ、それは何の意味もない戦略になる。マーケットを意識した強みを打ち手を考えないといけない。
注意すべきことは、マーケットがあるということはそれなりに競合も多いということ。
「打つ手の効果が一気に高まるようなポイント」というのはマーケットと競合、強みを考慮したポイントだと思います。
戦略の基本は、最も弱いところにこちらの最大の強みをぶつける事
最も弱いところとは競合の事やお客様の事を知らない限り弱みなど知り得られない。
最も効果のあがりそうなところ、つまりそれは自社自身のポジションであり、どんな人にどんなものを、どんな風にものやサービスを提供するか、自社、競合、お客様の状況をそれぞれ理解することが最大の強みをぶつけれる事に繋がるのだと思います。
戦略を立てるときには、「何をするか」と同じぐらい「何をしないか」が重要なのである
最も強みがあり、収益化できそうなところは何か。
あれもこれもというのは結局は戦力を分散させることになる。だからこそ一点に力を注ぎ余計なことに時間を取られないようにする。
何をしないかが重要というのは「何をするか」に集中することだと理解できます。
困難な選択を避ける
何が最も課題なのか。
それを判断する基準として何をすることが目的なのか、何をしたいのか?それをするためには、どの課題を解決することが最もインパクトがあるのかこういった視点で重要な課題をフォーカスしすることで戦略を立てる
ヒントへ繋がる。
amazon:良い戦略 悪い戦略