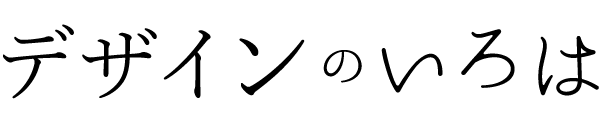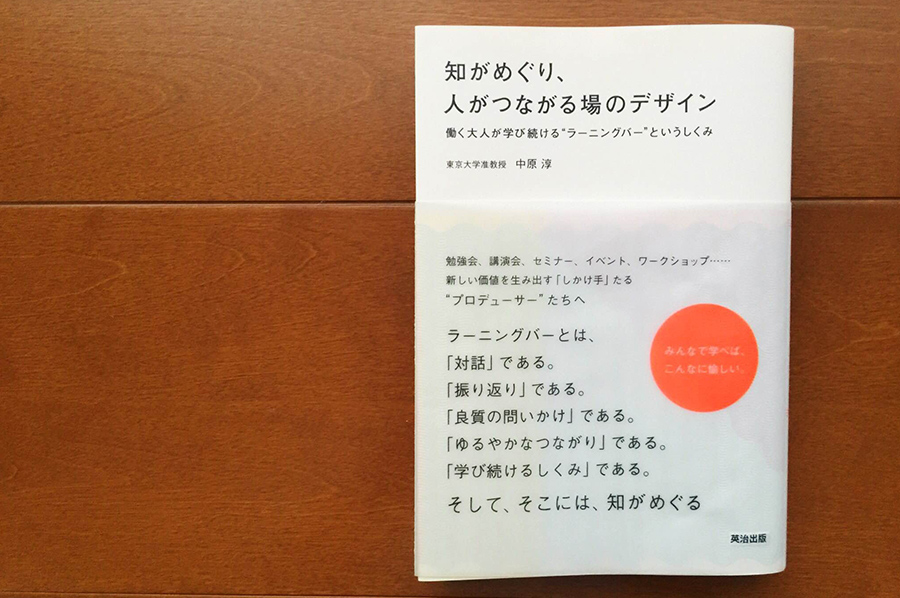本書は「ラーニングバー」という食べて飲みながら、みんなで学ぶという場の作り方や学び方が記載されている本です。
勉強会や講演、セミナー、セミナーワークショップなどの主催や準備をする方には、大変勉強になるところが多いのではないかと思います。
主催者でなくても普段の学び方のヒントも得られる本だと思います。
読んだ後は、全てでなくても、どこかのエッセンスを取り入れて実践したくなることは間違いないと思います。
ラーニングバーのコンセプト
ラーニングバーは講師の話をそのまま「覚える」ことではなく「自らの頭で考え」「対話して」「気づくこと」を目指している。
ラーニングバーでは学ぶことはもちろんなのですが、人ととの交流や学び方が、とても細かくデザインされている印象を受けました。
例えば初対面の人同士が、名刺交換をしやすくる為に場の雰囲気を作ったり、学び方も聞いて終わりだけでなく、考え、対話し、気づくという学びのプロセスが、とても良く練られています。
対話型ファシリテーションの手ほどきでもあったのですが、学んで忘れない様にするには「気づき」が大事で、その気づきまでがラーニングバーではしっかりとデザインされていると思います。
一般的な勉強会やセミナーの流れ
- 聞く
- 聞く
- 聞く
- 帰る
ラーニングバーの流れ
- 聞く
- 考える
- 対話する
- 気づく
このコンセプトの中でも「対話する」のルールが「自分はこう思う、こう感じる」「あえて判断を保留する」「勝ち負けや正しい・正しくない」を決める為に行うものでないと、あくまで主観をもとに話し客観的に話さない。という普段行われる対話と逆の形式なのが印象的でした。
こうする事で、「この人はこんな風に考えるのか」「なぜだろ?」と気づきを得やすい仕組みが上手く作られています。
そして、下記の言葉がとても印象的でした。
「スムーズではないやりとりこそが対話。対話の本当の意味は、他者との噛み合わない話をきっかけにして、自分が知っていること、そしていつの間にか「アタリマエ」の前提としていることに「裂け目」を入れること。
わかりやすく言えば、自分にとっての「アタリマエ」を疑い、その背後にあるものに気づくこと、それが対話の生み出す本当の効果です。」
また、通常、勉強会などは終わった後に懇親会がある事が多いのですが、本書はもともと仕事帰りの時間帯で行われる事が多いという事もあるのですが先に飲み物や食べ物を提供して人と人との交流を促し、後の対話がスムーズにできる。いわゆるアイスブレイクがなされているのも良く考えられていると思いました。
amazon:知がめぐり、ひとがつながる場のデザイン