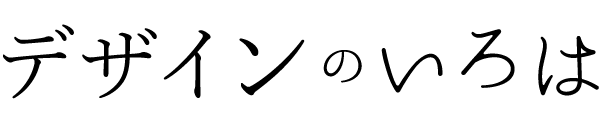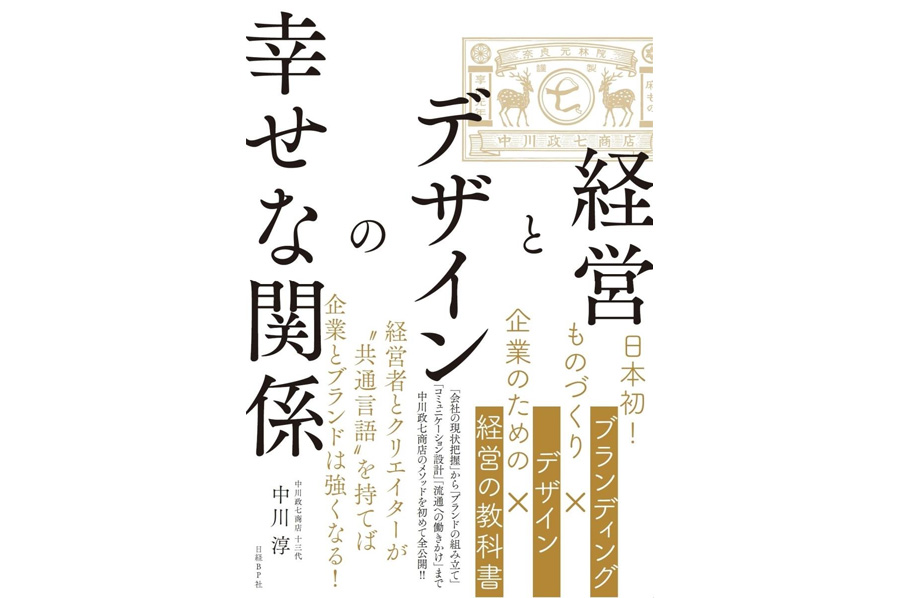画像引用:amazon経営とデザインの幸せな関係
中川政七商店さん代表の中川淳さんの本。
「老舗を再生させた十三代が どうしても伝えたい 小さな会社の生きる道」と少しだけ重なる内容のところもありますが、本書はブランディングの手法や考え方に比重が置かれた本です。
「小さな会社の生きる道」では実際にクライアントとどうやってプロジェクトを進めていったのか細かく描かれています。
どちらを先に読んでも良いと思いますが、どちらも読むと内容が反復してよりブランディングの考え方が身につくと思います。
問題解決の成否は、現状認識で7割方決まり
「小さな会社の生きる道」でもありましたが、自社が置かれている今の状況がどんな状況であるか先ず知る事が大事。
自社の強みであったり弱みであったり課題であったり競合であったり、しっかりと理解できていないと、そもそもの問題解決の方法を誤ってしまう。
当たり前なんですが、ほとんどの企業がしっかりとやれていない所ではないでしょうか。
場当たり的に新商品の開発を行ったり、やれブランディングだと行ってもうまくいかないのは、ほとんどがこの自社の分析が足りない所が多いと思われます。
本書では自社の分析に欠かせない決算書のおおまかな読み方などが記載してあり、まったく決算書の読み方がわからないという人でもわかりやすく書かれています。
課題が何で進むべき道はどこなのか、その道しるべとなる考え方が身につく内容ではと思います。
クライアントの考えを引き出す事前ヒアリングシート
恐らく確証バイアスを避ける為でもあると思うのですがヒアリング前に事前にクライアントに質問事項に記載してもらうことで、ありのままの意見を伺うというのも狙いの一つではないかと思います。
ヒアリングシートの内容的には「強み」「弱み」「課題」「競合」「どうなりたいか」など。実際にクライアントに書いてくださいとお願いした時にはクライアントだけでは書けないところも出てきそうだと個人的には思います。
ヒアリングのポイントは”徹底的に素人目線”で話を聞く
これはインタビュー系の書籍でも記載されてありますが、思い込み、わかったつもりにならないという事だと思います。
簡単そうに見えて最も難しいのではないかと個人的には思います。
確証バイアスしかり、聞く本人は全く意識していないことがほとんどで、どれだけ子どものように何度も問いを投げかけることができるかがヒアリングのポイントになると思います。
どんな風に自社の製品やサービスを購入していくのか
本書ではエンドユーザーの利用シーンをいくつか想定し、その中で最も企業側にインパクトがあるシーンを選択し流通経路のストーリーを描くやり方が記載されています。
デザインもこの方法は利用できると思います。
例えば「自社の製品はどんなお店で売りたいのか」という考え方から自然にデザインのトーンなども作成ができます。
100円SHOPの様なお店で売る様に考えられたプロダクトなのか、デパートで売る様に考えられたプロダクトなのか、それによって派生するwebデザインなどでも必然できにトーンがイメージしやすくなります。
強みの見つけ方
強みの見つけ方は本書では何度も出てきて印象に強く残っているのですが、その中でも「お客さんに響くポイントになっているか」というのは非常に印象的でした。
自社の強みとなると客観視できなくなるのもあるのですが、関係者以外から見た視点で「それ結局何がいいの?」となる事というのは多くあります。
自社の強みを見つけるだけでなく、それをお客さんに響くポイントまで消化できているかというのは簡単そうに見えて難しいと思います。
まとめ
ブランドを扱う本では割と見栄えの良いブランドの話などが書かれている書籍が多い中、経営からデザインまでの落とし込み、そしてブランドを作るにはどうしたら良いのかがまとめてある良い本でした。
個人的にはブランドというとすぐにアップルなどの名前が出るものがあまり好きではなく、この本はそういった意味でしっかりとブランドとは何か描かれている所がよかったです。
後半には対談の内容が記載されているのですが、そこでは「観察」の重要性が記載されています。
デザインの基本は「観察」と自身の中で思っているのですが、非常に共感できる内容でした。
amazon:経営とデザインの幸せな関係